◆本記事は、「門田隆将『死の淵を見た男』……日本を崩壊から救った男たち (1)」の続きです。(1)をお読みでない方は、こちらへ >
前回では、2011年3月11日の福島第一原発事故直後に、吉田昌郎(よしだ まさお)所長、斑目(まだらめ)原子力安全委員会委員長、菅直人首相(いずれも当時)の3名が、どのような「最悪の事態」を想定していたのか。それぞれの証言を重ね合わせて想像してみた。背筋に戦慄が走るほどの恐ろしいイメージであったと思う。
目次
外部電源復旧までの経緯
本書巻末には、事故発生から翌年8月までの関連する出来事が年表の形でまとめられている。3月11日から3月22日までの部分を抜き出してみよう。
<関連年表> (出典:門田隆将『死の淵を見た男』 ※赤字は引用者によるもの)
| 日 | 主な出来事 |
| 11日 | 午後2時46分、東日本大震災発生。津波により午後3時41分、全電源喪失 |
| 12日 | 1号機、水素爆発、原子炉へ海水注入。半径20キロ圏内に避難指示 |
| 13日 | 3号機も冷却不能となる。消防車から海水を注入 |
| 14日 | 3号機の原子炉建屋が水素爆発。2号機の格納容器圧力が最高使用圧力を超える |
| 15日 | 2号機で大きな衝撃音が発生し、圧力抑制室の圧力低下。4号機の原子炉建屋が爆発、火災。半径20~30キロ圏内の住民に屋内待避指示 |
| 16日 | 4号機で火災、3号機では白煙が噴出 |
| 17日 | 陸自ヘリが3号機の使用済み核燃料プールに水を投下。同時に陸自、空自が地上からも放水活動 |
| 18日 | 略 |
| 19日 | 東京消防庁、3号機使用済み核燃料プールに放水 |
| 22日 | 全6基で外部電源が復帰する。 |
事故発生からわずか5日間の間に、原発3機(1、3、4号機)で爆発が起こり、1箇所で火災発生。さらに2号機格納容器(原子炉本体)の内部圧力が上がり、いつ爆発するか分からない極めて切迫した状況だったことがよく分かる。
吉田所長と所員がおかれた状況
この切迫した状況の中、原子炉暴走を不眠不休で食い止めようとした吉田所長と所員たち。彼らがおかれた状況は、整理すると次のようなものであった。
- 地震後の津波で発電所の全電源喪失、非常用のディーゼル発電機も水没
- 停電により所内の全ての機器が作動不能、照明も点灯不能
- 地震と津波により瓦礫(がれき)が散乱、道路も陥没して通行困難。発電所内の施設、設備、機器等が損傷を受ける。
- 大津波の後、何度も押し寄せる中小の津波と繰り返される余震
- 原子炉冷却に使用する消防車3台の内、2台運行不能
- 放射能汚染を防ぐため、所員の作業時間の削減(1回2時間以内)と作業回数の制限
- 事態を十分に把握できない東京電力本社との意思疎通不足と軋轢
- 最大最悪の危機を迎えた3月15日に、菅首相が現地入りした混乱による事故対応の遅れ
こうして箇条書きしていくだけで、絶望的な気分になる。人はこのような劣悪で過酷な状況におかれた時、果たして精神的に耐えられるものなのだろうか。
所員の方々が超人的な努力を重ね、尽力された事実を知れば知るほど、驚きを禁じ得ない。彼らや自衛隊員達の命をかけた激闘を知りたければ、実際に本書を手にとっていただくことをお勧めする。
吉田所長は、次のように証言している。
「もう駄目かと何度も思いました。私達の置かれた状況は、飛行機のコックピットで、計器もすべて見えなくなり、油圧も何もかも失った中で機体を着陸させようとしているようなものでした。現場で命を賭けて頑張った部下たちに、ただ頭が下がります。」
(出典:前出)
疲労の極致にあった所員の様子を伝える、次のような証言もある。
免震重要棟のトイレは、真っ赤になっていた、と伊沢(引用者注=現場の作業責任者の名前)は言う。
「トイレは水もでないから悲惨ですよ。……(略)……とにかく真っ赤でしたよ。みんな、血尿なんです。あとで、三月下旬になって、水が出るようになっても、小便器自体は、ずっと真っ赤でした。誰もが疲労の極にありましたからね」
(出典:前出)
どんな事態になろうと、俺たちが原子炉の暴走を止めるー彼らを動かしている使命感と責任感に思いをいたすと、胸がしめつけられるようである。
最大の危機、所員の避難と最後まで残った69人(3月15日)
2011年3月15日午前6時過ぎ、前日に原子炉格納容器内の圧力が限界値を超えていた2号機から衝撃音が響き、容器内圧力の数値がゼロを示す。のちの検証によれば、この時2号機はなんらかの損傷により、全号機の中で最も多くの放射性物質を”放出”したとされている。
放出された放射能の汚染を恐れ、何もせずに手をこまねいていれば、「最悪の事態」が起こってしまう。
この最大の危機を迎えたとき、吉田所長は「自分と一緒に死んでくれる人間」の顔を思い浮かべていたと、述懐する。
「あの時、海水注入を続けるしか原子炉の暴走を止める手段はなかったですね。水を入れる人間を誰にするか、私は選ばなければなりませんでした。それは誰に”一緒に死んでもらうか”ということでもあります。こいつも一緒に死んでもらうことになる。こいつも、こいつもって、次々、顔が浮かんできました。」
(出典:門田隆将「日本を救った男ー吉田昌郎元所長の原発との壮絶な闘いと死」)
吉田所長は、「各班は、(必要)最少人数を残して退避!」と指示。免震重要棟(注=事実上の復旧センター施設)に残っていた600人以上のほとんどは福島第二原発へ退避。後には50名を越える技術系の所員が残った。
のちに欧米メディアから「フクシマ・フィフティーズ(Fukushima 50)」と呼ばれて所長と共に現場に残った人間は、実際には69人だった。
この時点から、死を覚悟し心を一つにした69名と、陸上自衛隊、航空自衛隊、東京消防庁職員らが、放射能汚染された原子炉建屋に何度も突入、海水による原子炉冷却作業を繰り返し、ついに最悪の事態は回避されたのである。
命を賭けなければならない時
門田氏は本書末尾に「終わりに」と題して、日本人が最悪の事態に放り込まれた時に発揮する、土壇場の「底力と信念」について言及している。少し長いが紹介させていただきたい。
私は、このノンフィクションを執筆しながら、「人間には、命を賭けなければならない時がある」ということを痛切に感じた。
暗闇の中で原子炉建屋に突入していった男たちには、家族がいる。自分が死ねば、家族が路頭に迷い、将来がどうなるかもわからない。
しかし、彼らは意を決して突入していった。自衛隊の隊員たちも、自分たちが引き起こした事故でもないのに、やはり命の危険もかえりみず、放射能に汚染された真っ只中に突っ込んでいった。
その時のことを聞こうと取材で彼らに接触した時、私が最も驚いたのは、彼らがその行為を「当然のこと」と捉え、今もって敢えて話すほどでもないことだと思っていたことだ。
(出典:前出)
この箇所を初めて読んだ時、小生は熱いものが胸にこみ上げてきたのを覚えている。命をかけた自己犠牲を「当然のこと」と考えている人たち。そんな人たちの思いを一つに束ねることができる、信念と志をもつリーダー。危機が過ぎれば、何事もなかったかのように日常生活にもどっていく人たち。他の国なら、彼らは国を救った英雄として顕彰される人々である。日本人ってなんて凄いんだ……。
まだ幼い孫たちが少年に成長したら、いつか吉田所長とフクシマ69のことを話してやろう。
「あのとき、あの場に、あの人達がいたからこそ、今の君と日本があるんだよ」と。
今日は7月6日、3日後の7月9日は吉田昌郎所長の5回めの命日である。氏のご冥福を心からお祈りし、哀悼の誠を捧げたい。
追記
本書と同じ内容を小・中学生向けに書き直した「吉田昌郎とフクシマフィフティ」(門田隆将、PHP研究所)もお勧めする。ぜひ子ども達に読んでもらいたい。



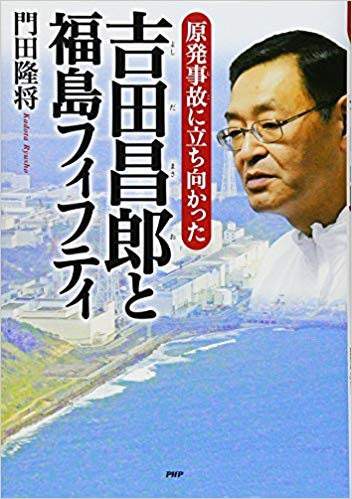






[…] 門田隆将『死の淵を見た男』……日本を崩壊から救った男たち (2) […]
[…] 門田隆将『死の淵を見た男』……日本を崩壊から救った男たち (2) […]
[…] 門田隆将『死の淵を見た男』……日本を崩壊から救った男たち (2) […]